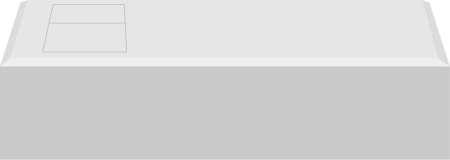葬儀で必要不可欠な物
葬祭部の板垣です。
ご葬儀がある場合に、必ず要る物があります。それは、棺(ひつぎ)です。棺とは、遺体を納めるための箱のことです。一般的に、何も入っていない状態のものを「棺」、遺体が納められた状態のものを「柩」と使い分ける事もあるそうです。
棺は古くから使われており、ツタンカーメンなどで有名な古代エジプトの時代から使用されています。日本でも古墳時代には棺に亡くなった人を納める形で発見をされています。
現在にように横になった状態で棺に納めてもらう形を寝棺といいます。江戸時代では主に土葬が主流だったのでの醤油樽のような桶型の棺(早桶)に座らせた状態で納められる座棺が主流だったそうです。身分の高い人の中では寝棺を用いられていた事もあったそうですが、今のように寝棺が主流になったのは火葬して弔うようになってからです。
最近では棺にも色々と種類があって木棺(木製の棺)や布張棺(布で覆われた棺)、エンバー棺(遺体の保存処理を施した棺)、エコ棺(環境に配慮した素材で作られた棺)などがあります。もみじ市民ホールでは、布張棺を使用しています。
後、地域にもよりますが、火葬場では棺に納めていただいた遺体でないとほとんどの場合、火葬ができません。これは、火葬場の炉が傷んでしまう事につながるので断られることがほとんどです。
もし葬儀の費用を抑えたいという方は、一度、もみじ市民ホールにご連絡いただくか、事前相談にお越しください!スタッフが当家のご希望をくんだプランで納得していただけるご案内をいたします。